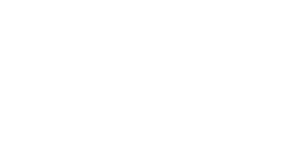戸籍の保存期間
最古の戸籍制度である「壬申戸籍」は1970年(昭和45年)に封印され、その後保存期間の経過により廃棄手続きがされており、一般に取得できる戸籍情報は「明治時代以降のもの」が中心となっています。
◎ 戦前の戸籍を取得する方法
本籍地の市区町村役場にて「除籍謄本」や「改製原戸籍」を請求するのが一般的で、これらの戸籍には『明治時代や大正時代』に編製されたものが含まれています。
◎ 大正時代以前に戸籍がない人の場合
具体的には現在確認できる戸籍は明治時代後半まで遡れることが多いですが、歴史的な背景や戦時中の焼失、保存期間の短縮等の影響で、すべての戸籍が完璧に保管されているわけではありません。
そのため大正時代以前の戸籍が存在しない場合は、理由として、戦争や災害による焼失、または制度改正に伴う記録の廃棄などが考えられます。
このようなケースは「焼失証明書」「廃棄証明書」を発行してもらうことで その戸籍が存在しないことを証明できます。
◎ 戸籍の附票について
戸籍の附票とは、戸籍にくっついているもので、戸籍内の全員の住所が記載されたものです。
戸籍の附票についても、保存期間が定められており、閉鎖されてから5年間と決められています。ただ、戸籍謄本にくっついている戸籍の附票は「戸籍謄本が存在している限り、保存されています」
そして戸籍謄本が閉鎖されると、戸籍謄本から「改製原戸籍」に名称が変わると戸籍の附票も改製原附票という名称に変わります。
改製原戸籍の保存期間は、改製された年度の翌年から150年です。(平成22年6月1日から)
それ以前の改製原戸籍は、
‣明治19年、明治31年式戸籍(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改製したものを除く)=80年
‣大正4年式戸籍で原戸籍になったもの
(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改製したものを含む)=50年
‣昭和23年敷戸籍で原戸籍になったもの(戸籍をコンピュータ化したもの)=100年
戸籍の附票が改製原附票になってから5年が経過すると、保存期間を過ぎる為、役所側で廃棄され、その後誰も取得することができなくなります。(※役場によっては、保存期間の5年を過ぎていたとしても廃棄せず残している役所もあります。)